かつて「糖尿病」といえば中高年に多い病気とされてきました。しかし、近年では小学生の糖尿病が確実に増加しており、医療現場でも深刻な問題として注目されています。
背景には、食生活の変化・運動不足・肥満など、現代の子どもたちを取り巻く環境の影響があります。ここでは、小児糖尿病の種類・症状・原因・予防法を医学的な視点から詳しく解説します。
小児糖尿病とは?──1型と2型の違い
小児糖尿病は大きく「1型糖尿病」と「2型糖尿病」に分けられます。
● 1型糖尿病:自己免疫が原因でインスリンが作れない
1型糖尿病は、体内の免疫システムが誤って膵臓のβ細胞を攻撃し、インスリンを作れなくなる自己免疫疾患です。
小児糖尿病のうち、特に発症が急激で、やせ型の子どもに多い傾向があります。発症のピークは10〜14歳ですが、小学生でも増加傾向です。
主な症状は次の通りです:
-
異常な喉の渇き(多飲)
-
トイレが近くなる(多尿)
-
急激な体重減少
-
倦怠感や集中力の低下
発症初期には風邪や疲労と見分けにくい場合もあり、見逃されやすい点が課題です。
● 2型糖尿病:生活習慣が原因でインスリンが効きにくくなる
かつては「成人病」と呼ばれた2型糖尿病が、現在では小学生にも見られます。
原因は主に、
-
高カロリー・高糖質な食事
-
スナック菓子や清涼飲料水の過剰摂取
-
運動不足や肥満
などによる「インスリン抵抗性」の増加です。
特に日本では、肥満を伴う小学生の約20〜30人に1人が糖代謝異常を指摘されるデータもあります。
小学生に糖尿病が増えている理由
1. 食生活の欧米化
朝食を抜いたり、パン・ジュース・ファストフードなど糖質中心の食生活が増えています。
また、甘い飲み物(スポーツドリンク・炭酸飲料など)には多量の砂糖や果糖ブドウ糖液糖が含まれており、これが血糖値の乱高下を引き起こします。
2. 運動不足
文部科学省の調査では、小学生の体力は1980年代より低下傾向にあります。
外遊びの減少、ゲームや動画視聴の時間増加により、エネルギー消費量が極端に少なくなっていることが背景にあります。
3. 睡眠不足と生活リズムの乱れ
夜更かしや朝食抜きは、ホルモンバランスの乱れを招き、インスリンの働きを妨げることが知られています。
特に「睡眠不足は肥満リスクを約2倍に高める」という報告もあり、間接的に糖尿病の発症を促進します。
4. 遺伝的要因
糖尿病の家族歴がある場合、子どもにも発症リスクが高いことが分かっています。
特に2型糖尿病では、遺伝と生活習慣が相互に影響します。
小児糖尿病の症状に早く気づくには
糖尿病は初期症状が分かりにくいため、気づいた時には進行しているケースもあります。
保護者が注意すべきサインは以下の通りです:
-
水やジュースを異常に欲しがる
-
トイレの回数が増えた
-
体重が減ってきた
-
疲れやすく、元気がない
-
学校の集中力が落ちている
-
傷の治りが遅い
これらが続く場合は、小児科または小児内分泌科を受診し、血糖値やHbA1c検査を行うことが大切です。
早期発見・早期治療が子どもの将来を守る
糖尿病を放置すると、将来的に腎臓病(糖尿病腎症)・網膜症・神経障害などの合併症につながります。
しかし、早期に発見し、生活習慣を整えることで進行を防ぐことは可能です。
1型糖尿病では、インスリン注射や持続型インスリンポンプ(インスリンポンプ療法)によって血糖コントロールを行います。
2型糖尿病の場合は、まず食事療法・運動療法が基本です。重症例では内服薬を用いることもあります。
学校や家庭でできる小児糖尿病の予防法
● 食生活を整える
-
朝食を抜かない
-
ご飯や野菜を中心とした和食ベースの食事
-
清涼飲料水・お菓子を控える
-
食事時間を一定に保つ
● 運動を習慣化する
-
1日1時間以上、外で体を動かす
-
家族でウォーキングやスポーツを楽しむ
-
スマホやゲームの時間を制限する
● 睡眠をしっかりとる
-
小学生は1日9〜10時間の睡眠が理想
-
夜更かしを避け、成長ホルモンの分泌を促す生活リズムを保つ
保護者と学校が連携を
糖尿病を抱える小学生が増える中で、学校現場での理解と支援も欠かせません。
血糖測定やインスリン注射が必要な場合、教職員が安全に対応できる環境を整えることが求められます。
また、保護者と医療機関、学校が情報共有を行うことで、子どもが安心して学べる環境を作ることができます。
まとめ:今こそ、子どもの「血糖値」を意識する時代へ
小学生の糖尿病は、もはや珍しい病気ではありません。
生活習慣の変化によって、“大人の病気”が子どもにも広がっているのが現実です。
しかし、食事・運動・睡眠を見直すことで予防は十分可能です。
家庭や学校が一体となって、子どもたちの健康を守る取り組みが今、求められています。
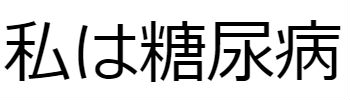
Leave a comment